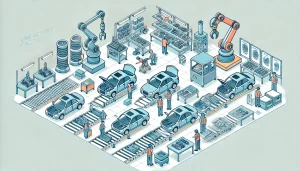標準原価とは?
「標準原価」という言葉を聞いたことがあるかたは多いと思いますが、それがいったい何なのかを説明できる人は少ないかもしれません。
一般に「原価」と言われるものには、「実際原価」と「標準原価」の2種類があります。
「実際原価」というのは、その商品を製造・販売するのに実際にかかったコストのこと。
これは文字通りなのでわかりやすいと思います。
これに対して「標準原価」というのは、その商品をつくるのにこのくらいのコストがかかるはずだという見積もりです。
見方を変えれば、原価の目標と言ってもいいでしょう。
標準原価を定めることは、利益を残し、経営改善を日々行うための、必須条件です。
というのも、標準原価の中には「材料費はこのくらい」「労務費はこのくらい」といった、計画が含まれているからです。
このような計画があるからこそ、その計画からずれてしまっているかどうかを評価できますし、ずれてしまっている場合に修正しようと取り組むことができるようになります。
たとえば、標準原価を計算した結果、ある作業にかけてよい労働時間が1商品あたり15分だったとします。
ある日、この作業にかけた労働時間がのべ20時間だったとします。
1商品あたり15分で、のべ20時間なので、20時間÷0.25[時間/個]=80[個]の商品を処理できているはずです。
が、実際には75個しか処理できていなかったとしたら――実際原価が標準原価より大きくなってしまいます。
そのぶん利益が少なくなります。
標準原価は、日々の改善のための指標です。
経営改善の第一歩として、ぜひ作成してみてください。
標準原価設定の第一歩:変動費
標準原価を設定するうえでは、変動費と固定費に分けて考えることをお勧めしています。
損益計算書の項目に沿って考えても問題はないのですが、シミュレーションをする場合にややこしくなってしまいます。
変動費と固定費に分けておくことで、損益分岐点などの値を見ながら標準原価を設定することができるようになります。
参考に、グーグルスプレッドシートのフォーマットを用意してみました。
以下のURLからアクセスできます。
編集はできないようにしているので、ダウンロードしてお使いください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rxATB8ajdBiFjJhXAhQXTxWN_5r0WWNvfN_Re3fHTd8/edit?usp=sharing
変動費を考えるうえでは、以下のように、「何に比例するのか」によって変動費を分類しておくと、なおシミュレーションがやりやすくなります。
- 生産規模に比例するもの(材料費、労務費、製造に必要な動力光熱費、…)
- 販売量に比例するもの(包装梱包資材費、送料、保管料、…)
- 販売金額に比例するもの(販売手数料、消費税、…)
生産規模に比例するものと販売量に比例するものはどちらも同じように「商品1つあたり」を基礎に考えられることが多いですが、計算の仕方を変えたほうがよい業界や商品もありえます。
たとえば農業では、種や肥料などの材料や労働力は農地の面積に比例して投入するのに対して、農産物の出来高(=販売量)は天気などの要因によって左右されます。
この場合、生産規模に比例する変動費は、面積に比例させるようなシミュレーションにしておくべきです。
あるいは、電子書籍、音楽、ソフトウェアなどの電子データや著作物は、生産したものをいくらでもコピーできるため、生産規模に比例する変動費を「商品1つあたり」で計算することができません。
こうした場合は、変動費は作品1つをつくるのに必要な人件費や外注費などのオリジナル作品1つあたりで考え、販売量に比例する変動費はサービスの使用量などコピー1つあたりで考えるとよいでしょう。
そうして、生産規模と販売量の関係を求めるための変数も用意しておきます。
農業の例なら「面積あたりの販売量」、音楽の例なら「オリジナル作品1つあたりのコピー販売量」といったものです。
このような変数を入れておくことで、生産効率や販売効率が原価に与える影響をシミュレーションできるようにもなります。
損益分岐点を求めるには固定費も計算する
原価を求めるときには、一般には変動費まで求めれば十分です。
しかし、利益が残るかどうかを見積もり、適切な事業規模を検討するうえでは、固定費も評価することが必須です。
変動費を下げる基本的な手段として、設備投資をして製造効率を高めることがあります。
そうすれば、高い確率で変動費を下げられ、売上から変動費を引いた利益(限界利益と言います)を向上させられます。
しかし、設備投資をすれば、そのぶん減価償却費として、固定費が増加します。
もし変動費が小さくなっても、それ以上に固定費が大きくなれば、利益は減ります。
ですから、設備投資をして固定費が増える場合には、生産量を増やすことで、限界利益の増加分を固定費の増加分よりも大きくしなければいけません。
固定費を計算するうえでも、ややこしいことがあります。
「複数の商品や部門がある場合に固定費をどのように案分するか」という問題です。
適切な案分のしかたは目的や状況により異なりますが、人件費ないしは費やしている労働時間によって案分するのがよいかと思います。
売上比例での案分は簡単ですが、高単価の優良な商品に多くの固定費を案分してしまって商品ごとの利益の差を小さくしたり、売上が立っていない新規事業について楽観的な数字を示したりする可能性があるので、あまりお勧めしません。
このように文字だけで説明してもなかなか分かりにくいので、上記のサンプルフォーマットなどで実際に数字をいじりながら、自社の条件に合うやり方を模索していただければと思います。
より突っ込んだ分析をしてみたいという場合は、お問い合わせください。