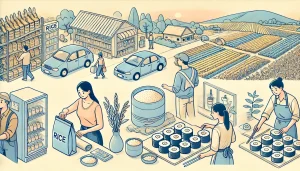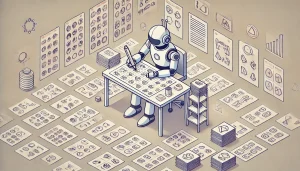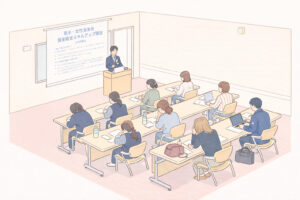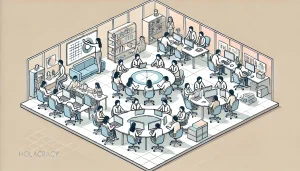「ウェルビーイング」という言葉をよく聞くようになりました。
英語になじみのある人でしたら知っている単語だと自然に受け入れられるでしょうが、そうでないと「またカタカナ語か」とうんざりかもしれません。
たしかに、はたしてウェルビーイングという英語をカタカナのまま使うべきかということについては議論の余地が大きいと思います。
しかし、ウェルビーイングが重要な概念だということは、言を俟たないことです。
本書、山田鋭夫の『ゆたかさをどう測るか』は、経済学者の立場からウェルビーイングを論じたもの。
ウェルビーイングが大事だということは、たとえば、「従業員のウェルビーイングを追求することが会社の利益にも結び付く」といったかたちで理解されている場合が多いと思います。
つまり、利益が目的で、ウェルビーイングは利益という目的に至るための手段だ、というわけです。
しかし、本書を読むと、これは実は反対かもしれないと思わされます。
ウェルビーイングが目的であって、利益はウェルビーイングという目的に至るための手段だ、というわけです。
経営者という立場からは、そんなことは言っていられない、それはきれいごとだ、と思われるかもしれません。
しかし、個人として考えてみてください。
お金と幸せのどちらが目的かと訊かれたら、誰もが幸せだと答えるでしょう。
それならば、ウェルビーイングを追求して、その中の大事な要素として、しっかりと利益ないし所得を確保する、というのが本来のはずです。
ただし、本書で紹介されているさまざまの研究の中では、金銭はウェルビーイングの要素と考えられています。
たとえば国連の「世界幸福度報告」では、主観的な幸福(ざっくりと言えば、「あなたは幸せですか」といった回答に人がどのように答えるか)に寄与する要因が統計的に分析されていますが、どのような国でも「GDP」の幸福への寄与が他の要因よりも大きいそうです。
お金だけでは幸せになれるとは限らないけれど、お金がないと幸せになることは難しいのです。
モチベーションの「動機づけ要因」と「衛生要因」ということを聞いたことがあるかたは多いかもしれませんが、これも同じ文脈で理解できます。
動機づけ要因というのは、それがあるとモチベーションがゼロからプラスに高まっていくもの。
衛生要因というのは、それがないとモチベーションがゼロからマイナスになってしまうもの。
つまり、衛生要因はあって当たり前のもの、動機づけ要因はプラスアルファのものです。
さて、お金がどちらなのかと言えば……有名な話ですが、お金は衛生要因だとされています。
つまり、給与は少ないと不満が出るけれど、多ければ多いほどモチベーションが高まるかというとそんなことはない。
ふつうの人にとって、お金は必要な額があればよいのです。
それでは、幸せに近づくうえでも、モチベーションを高めるためにも、お金以外の要素は何なのか、ということが問題になります。
先の「世界幸福度報告」によると、幸福度が高い国(北欧に多いです)での幸福への寄与率が大きい要素は、大きい順に、GDP、福祉、選択自由、健康寿命、……となっています。
本書で語られているわけではありませんが、面白いと思ったのは、日本の調査ではこの順番が少し異なっていることです。
GDP、福祉までは同じなのですが、日本のデータでは、その次が健康寿命、次が選択自由、となっています。
日本では幸福であることの理由として「寿命が長く健康であること」を挙げている人のほうが、「自由な選択ができること」を挙げている人より多いわけです。
ということは、日本では、より幸福度が高い国に比べて、自由な選択ができていると感じている人が少ないのかもしれない。
もしそうなら、自由な選択を可能にしていけば、より幸福度が高まるのかもしれない。
マクロな研究をもとに因果関係を導き出すことはできませんが、私の直感としては、この議論は正しそうな気がしています。
選択の自由を高めることが、自身の、また組織の、ウェルビーイングを高めることにつながる。
あまりリスクが伴わない範囲で、この仮説を検証してみてはどうでしょうか。