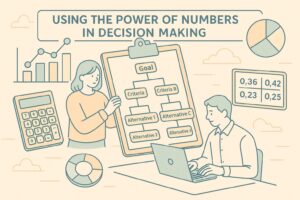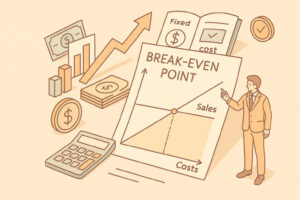経営技術はあってもコンセプト化ができない日本
最近岩尾俊兵の『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』を読みました。
日本は優れた経営技術を多々生み出してきたものの、それをコンセプト化することはあまり得意ではない。
それに対してアメリカは、経営技術を生み出すことと同時に、コンセプトをつくる能力に長けている。
だから、日本発の経営技術がアメリカにおいてコンセプト化されて、それがアメリカ発のものとして日本に逆輸入されるような事態も起こっている。
日本も個別具体的なものから普遍的一般的なコンセプトを生み出す力を養うべきだ。
ざっくりと言うと、こうしたことが述べられています。
これには非常に共感するところがありました。
たとえば、最近メールマガジンでも書きましたが、いまアメリカでベストセラーとなっているMel Robbinsの『The Let Them Theory』という本は、「Let Them」という強力なコンセプトを打ち出しています。
他者は変えることができないし、他者の問題を肩代わりすることは多くの場合その相手の成長を阻害することはあっても促すことはない。
だから他者の態度に気を煩わせても仕方がないし、他者の課題や問題に口を出すべきではない。
こうした態度を「Let Them」、つまり「させておけ」という、たった2音節の分かりやすく覚えやすいコンセプトにしたわけです。
これは(著者が意識したかどうかは知りませんが)アドラー心理学の「課題の分離」と同じような概念です。
学術的には「課題の分離」のほうが精緻な概念と言えるでしょうが、実用の観点からすると、ムッとすることがあったときに「課題の分離をしよう」と考えるよりは、「Let Them」と言って済ませるほうが実践しやすいしスマートです。
これがコンセプトの力です。
『ザ・ゴール』のもとはトヨタ生産方式
『日本企業はなぜ「強み」を捨てるのか』では様々な事例が紹介されています。
一例を挙げると、エリヤフ・ゴールドラットの『ザ・ゴール』。
これは生産性改善のポイントを「ボトルネック」や「スループット」といったコンセプトをもとに論じた名著で、日本でもかなり読まれたのでご存じのかたも多いと思います。
私はQCを学んだりコンサルタントとして実践していたりするので感じていたことなのですが、このコンセプトは、トヨタ式などの改善とかなり近いものです。
そして、本書によると実際に、ゴールドラットはトヨタ生産方式を学んだことをきっかけとして自身の生産性改善の体系をつくったのだそうです。
さて、改善はそれ自体KAIZENとして国際語にもなっていますが、そのコンセプトとしてはボトルネックやスループットといった概念のほうが分かりやすいと感じます。
強力なコンセプトがあると、人びとの理解が促進され、実践にも結び付きます。
コンセプトが無いとメールを無視される?
個人的な体験からも、コンセプトをつくることは重要だと思っています。
私がはじめて勤めた会社はフランス資本でした。
日本で3か月ほど研修を受けたら、そこから1年間、フランスのグループ企業で仕事をしました。
そのため、そのフランスの会社での働き方が自分のスタンダードとして身についています。
フランス人と仕事をしたことがある人から、よく、フランス人にメールを送ってもなかなか返事が来ない、という不平を耳にすることがあります。
その原因はいろいろありますが、前提として、フランスは権利の国であり、自身の権利のために、仕事を必要以上にしないということがあります。
フランスの労働時間は週35時間が基本です。
キャリア組の人は別として、ふつうの務め人は、この時間を超えて働くことはありません。
もし残業していたら、責められるのは適切な管理ができていない上司のほうです。
だから、上司としても部下の労働時間の超過は極力回避しようとします。
もし成果が上がらなければ、部下の側には解雇されるリスクがあります。
降格や解雇のリスクは、日本とは違って現実にありえるものです。
実際に、私もフランスの職場で降格したり解雇されたりした人を見てきました。
このような、決められた時間で最大限の成果を上げることが求められる環境では、無駄な仕事をしている暇はありません。
だから、対応する必要がないと思ったメールは無視をするのが当然のことになるのです。
フランス人にメールを送って反応がなかったとしたら、主に二つの可能性があります。
対応するほどの重要性が無いものであったか、重要性が正しく伝わらなかったかです。
前者のようにそもそも相手が関心をもたない内容だったのであれば、仕方がありません。
しかし、コンセプトを明確に伝えることを苦手とする日本人からのメールの場合、重要性を正しく伝えられなかった可能性も高いです。
これは、私自身も経験があります。
短い言葉で、端的にメッセージを伝えられなければ、相手は重要性を判断する前に読むのをやめてしまうかもしれません。
私は次に日系の会社で日本の顧客を相手に仕事をするようになりました。
そこで戸惑ったのは、「言わなくても分かって当然」といった感じで、コミュニケーションが省略される場面が非常に多いということです。
(反対に、あいまいなところが残らないようにと私がいろいろな質問をしたら、面倒くさがられたり、攻撃的な態度だと思われたりしました。
私はもともとフランス文学をやっていたこともあり、フランス帰りの知り合いも多いですが、だいたいの人が日本に帰ってきてから「攻撃的になった」と言われた経験をもっているようです。)
たしかに、日本という文化的な同質性がたいへん高い国で日本人だけで仕事をするのであれば、「暗黙の了解」で何とかなる場面は多いと思います。
しかし、ときにプロジェクトの目的や会議の議題など、極めて本質的なことがあいまいなままになっている場面あります。
こうしたとき、「コンセプトは何か?」という問いをあえて投げかけてみるとよいと思います。
それに対する答えが人によって違ったり、そもそも答えが出てこなかったりしたら、それは大きなリスクです。
しかし、この問いに答える過程で、軌道を修正できるでしょう。
仕事の質やコミュニケーションの質を高めるために、「コンセプトを問う」ことを、習慣にしてみてください。