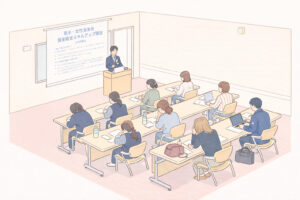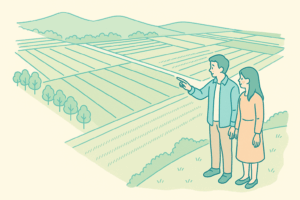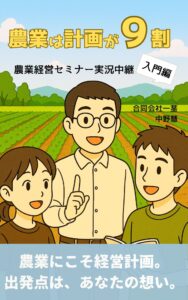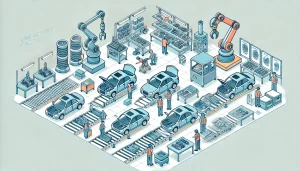経営をデザインする前提としての損益分岐点
経営をする上で、損益分岐点の考え方を理解することは極めて重要です。
しかし、小規模な企業では「自社の損益分岐点を計算したことがある」という経営者にはあまり出会ったことがありません。
私はこれまで農業界を中心に様々な事業者の経営分析をお手伝いしてきましたが、自社の損益分岐点を把握している経営者は僕わずかでしたし、損益分岐点を計算していると言う経営者も、実際には間違った理解や計算をしている場合が多々ありました。
損益分岐点がわからないと言うことは、「どのくらいの売上を実現すれば利益が残るのかがわからない」ということです。
もし赤字なら、いま掲げている売上目標を達成しても黒字にならないかもしれません。
いま黒字だったとしても、どのくらいの余裕があるのか、どのくらいのリスクを取ることができるのかがわからないということになります。
反対に、損益分岐点を把握していれば、目標設定が適切なものになります。
計画や予算を考える上で、損益分岐点は必ず把握しておくべきものです。
損益分岐点の計算は厳密にやろうとするとなかなか難しいものですが、ある程度ざっくりとした計算でもそんなに大きく外れることはありません。
ここでは、決算書をもとに損益分岐点を計算するプロセスを説明します。
なお農業を念頭に説明していきますが、どのような産業でも考え方は同じです。
損益分岐点って何?
まず、念のためですが、損益分岐点というもの自体について簡単に説明しておきます。
損益分岐点というのは、「利益を確保するために必要な最低限の売上ないしは販売量」のことです。
金額のことを指す場合もあれば販売量のことを指す場合もあるので、より厳密に言おうとすれば、「損益分岐点の売上高」とか「損益分岐点の販売量」といった表現をすることになります。
まずは経費を変動費と固定費にわける
損益分岐点を計算する上で必要になるのが、変動費と固定費の考え方です。
具体的な数字を用いて説明する方がわかりやすいと思うので、シンプルな例をあげます。
「りんごを50円で仕入れて100円で販売する」というビジネスを考えてみます。
この事業を1人で行い、本人の人件費以外の固定的なコストは一切かからないとします。
仮に、この事業者が生活をしていく上で年間200万円必要だとします。
すると必ずかかるコスト、つまり固定費は年間200万円ということになります。
次に変動費です。
実際には商品の運送料とか袋代など、商品をつくったり販売したりするのに伴う経費は色々ありますが、今回はわかりやすくするために、りんごの仕入れ代金である1個あたり50円だけがかかるとします。
すると、りんごを100円で売って得られる利益は50円となります。
このように収益から変動費だけを差し引いた利益を「限界利益」と言います。
さて、りんごが100個売れたとすると、限界利益は100×50で5000円となります。
100個売れると結構売れた気分になるかもしれませんが、5000円の限界利益では不十分です。
なぜなら、この事業者は生活費として200万円稼がなければならないからです。
それでは、りんごをいくら分売れば生活費、つまり固定費である200万円を確保することができるでしょうか?
この例は非常にシンプルなので、400万円の売上があれば、その半分の200万円が限界利益となり、固定費をカバーできると暗算で求めることができます。
これと同じことで、「限界利益をどのくらい積み上げれば固定費よりも大きくなるか」を計算することによって損益分岐点を求めることができます。
損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率
計算の方法としては、「固定費」を「限界利益率」で割ります。
今回の例では、固定費は200万円でした。
一方の限界利益率というのは、売上のうちの何%が限界利益になるのかを示すものです。
今回は100円の売上に対して50円が限界利益なので、50÷100を計算して、限界利益率は50%だと求められます。
固定費の200万円が売上高の50%になるような売上高が損益分岐点となるので、200万円÷50%で400万円という計算になるわけです。
損益分岐点販売量=固定費÷商品1つあたりの限界利益
あるいは、販売個数を意識した説明のほうがよりわかりやすいかもしれません。
今回の例では、りんごを1個売るたびに50円の限界利益が生じます。
この50円の限界利益をたくさん積み重ねて200万円にすることができれば、固定費として必要な200万円をカバーすることができます。
そこで、目標となる200万円の固定費をりんごを1個あたり50円という限界利益で割ります。
すると4万個という答えが出てきます。
念のため検算をしますが、50×4万で200万になります。
りんごを4万個売るということは、売上高としては4万×100=400万円となります。
計算式の点では、最初に説明したように損益分岐点売上高=固定費÷限界利益率というやりかたのほうが簡単ですが、その意味を理解する上では、後者のように「商品あたりの限界利益をいくつ積み上げれば固定費用カバーできるか」という考え方のほうが分かりやすいと思います。
決算書をもとに変動費と固定費を概算する
さて、このような損益分岐点の計算の基本を抑えた上で、実際に損益分岐点を計算するステップに進みましょう。
ここまで説明してきたように、固定費と変動費の金額がわかれば損益分岐点を計算できるわけです。
そこで、決算書(より具体的には損益計算書)を用意して、その1つ1つの科目について、変動費か固定費かと仕訳をしていきます。
このとき、実際のところは変動費と固定費が完全に分かれるわけではありません。
光熱動力費を考えてみましょう。
商品の製造や調整をする上で、多くの場合電力を使うことになると思いますが、電気料金は変動費と固定費両方の性格をもっています。
まず、電気代の計算式がそもそも基本料金と従量料金によって計算されるようになっています。
また、機械を動かすのに必要な電力は変動費的な性格をもっていますが、作業場や事務所の照明の電力は固定費でしょう。
このように、1つの勘定科目を取ってみても、それが100%変動費であるとか100%固定費であると言ったことはあまりないものです。
これをわけられればより良いかもしれませんが、シミュレーションをする上では「えいや」と、これは変動費、これは固定費といった形で2分していってもあまり支障はありません。
典型的な変動費
典型的な変動費としては、第一に材料費があります。
農業なら種苗費や医療費や農薬費といったものです。
これらは、生産量を増やそうとすればそれに比例して増える経費であり、まさしく変動費です。
農地を借りて生産しているなら農地の賃借料も変動費になります。
販売時にかかる販売手数料も「売上の何パーセント」といった形でかかってくるのが普通なので、変動費です。
農業に限らず一般に、材料費や販売手数料は基本的には変動費です。
迷ったら労務費は固定費に
金額がそれなりに大きくて判断に迷うのは、労務費です。
一般的には、生産量や販売量を増やそうとすると、それに伴って人を雇用することになるので、労務費は変動費であるとみなされることが多いです。
しかし、実際のところは、パートやアルバイトといった人材でも「仕事が増えたから倍の人数に来てもらう」とか「仕事がなくなってきたからしばらく来ないでもらう」といったような柔軟な調整はできないものです。
そこで、本当にスポット的な感じで来てくれる人たちへの報酬でない限りは、労務費やその他の人件費は固定費として考えたほうがよいです。
なお、個人事業の場合は、経営者本人の収入が損益計算書上の経費として載りません。
しかし、損益分岐点を計算するうえでは、生活費などでどのくらいかかるのかを見積もった上で、その金額を人件費として考えておくとよいでしょう。
このようにして経費のうちのどれが変動費かを分類したら、次は固定費ですが、経費を変動費と固定費の2つに分けて考えるのですから、変動費以外は全部固定費として考えればよいです。
損益分岐点の計算例
仮に、売上が1000万円で経費が1100万円、つまり100万円の損失が出ている事業者がこの分析を行ってみたとします。
その結果、1100万円の経費のうち変動費が600万円、固定費が500万円だったとします。
すると、限界利益は1000万円-600万円=400万円、限界利益率は400万円÷1000万円=40%となります。
ここまでで準備ができたので、損益分岐点を計算します。
固定費の500万円を限界利益率の40%で割ります。
すると、500万円÷40%=1250万円となります。
現在の売上高が1000万円なので、売上を250万円分、25%高めないと利益が出ないわけです。
さて、このような結果が出たとして、「だからどのように改善するか」ということについては、当然ですがケースバイケースなので一概に言うことはできません。
しかし、損益分岐点や、その前の段階として限界利益率などの数値がわかっていると、どこを改善することが有益なのか、見当をつけることができるようになります。
当社にご相談いただければ、こうした損益分岐点の大まかな分析は無料で行っていますが、それほど難しいことではありません。
相談されるにしても、ここまではご自身で実施された上でいらっしゃるほうが、より相談が有益な機会になると思います。
まだ挑戦したことがないというかたはぜひ試してみてください。