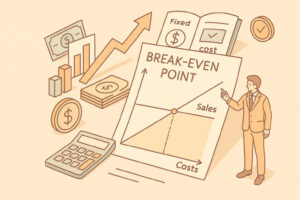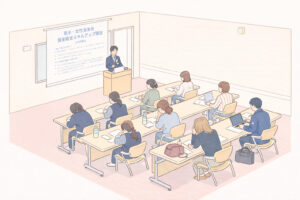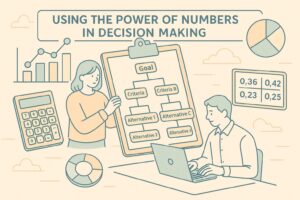ChatGPT Agent とは?
2025年7月17日、OpenAI は ChatGPT に新機能「Agent モード」を追加しました。
https://openai.com/index/introducing-chatgpt-agent/
これは従来のチャット機能に加え、ユーザーに代わって複数のツールや外部サービスを組み合わせ、実際の業務を完了する「行動型」AI です。
従来の ChatGPT がテキストで回答を返すだけだったのに対し、Agent モードでは内蔵の仮想コンピュータとツールを活用してウェブサイトを閲覧したり、フォーム入力やコード実行を行ったり、Gmailやカレンダーなどのアプリと連携して複雑なタスクを完了できます。
OpenAI の公式発表でも、既存の「operator」「deep research」といった機能を統合し、多段階の調査やウェブ操作を自動で遂行できることが強調されており、ビジネスにおける活用の可能性が一気に広がりました。
農業経営においても例外ではなく、生産や経営の現場で新たな価値を生み出すと期待できます。
ChatGPT Agent の特徴
仮想コンピュータと複数のツールを搭載
Agent は独自の仮想マシン上で動作し、ブラウザや端末など複数のツールを切り替えながらタスクを完了します。
これにより、ブラウザでウェブページを閲覧したりフォームを入力する操作を人間のように実行できます。
さらにコードを実行してデータ分析やファイル作成を行うことも可能です。
個人的に便利だなと思っているのは、プロジェクトの内部でも Agent を利用できることです。
つまり、プロジェクトにさまざまなファイルをアップロードしたり、前提となる指示を入力したりしておけば、Agent はその情報を参照したうえでアウトプットをしてくれるわけです。
外部アプリとのコネクタ連携
Gmail、Google Drive、GitHub、カレンダーなど外部サービスへ接続でき、必要なデータを取得したりメール送信などの処理を自動化できます(私自身は、 Google Workspace を使用しているため、メールやカレンダーなどは Gemini で連携するので十分だという印象を持っていますが、 Agent にてより強力な自動化ができそうな気はします)。
マルチステップのワークフロー実行
ブラウジング、コード実行、ドキュメント生成といった機能を組み合わせて、情報収集からの報告資料作成や、プログラムの設計・開発・ファイル生成、イベントの準備とそのための買い物など、複数ステップにわたるタスクを実行できます。
タスクの途中で購入や送信などの重要な操作をする際には、ユーザーに確認を求める安全機能も備えています。
有料プラン限定
Agent モードは2025年7月現在、ChatGPT Pro・Plus・Team の有料ユーザーのみが利用可能です。
そのうち無料ユーザーでも使用できるようになるかもしれませんが、まだ少し先のことにはなりそうです。
Plus ユーザーは月額20ドル、つまり3000円程度なので、優秀な秘書をこの金額で雇えると思えば破格です。
この機に少しだけ試してみるのもよいと思います。
農業経営における活用
さて、この Agent を農業経営に活用する場面としてどのようなものがあるか、考えてみましょう。
仮想コンピュータと外部連携機能を備えた ChatGPT Agent を活用すれば、複数のアプリやデータを横断して処理する作業を自動化でき、生産性向上が期待できます。
まだ具体的な活用事例はほとんどないかと思いますが、今後の可能性として、以下では、生産管理と経営管理の側面から活用アイディアを紹介します。
生産管理への活用アイディア
農業資材のオンライン購買自動化
種苗や肥料、農薬などの発注業務は、生産計画や在庫管理と連携しつつ、気象条件や市場価格を考慮する必要があります。
このプロセスを Agent によって自動化できるかもしれません。
生産計画や在庫情報をもとに必要量を計算したうえで、ブラウザで販売サイトを閲覧し、価格や納期を比較し、注文手続きを進める、といったことが自動化されれば、ミスがかなり減らせそうです。
栽培データの収集・解析とレポート作成
IoT センサーやアプリなど、もともと使用している機器・ソフトウェアがあれば、それらから温湿度などのデータを取り込み、最適な管理指標を算出する、といったことができるかもしれません。
今でも同様のことができなくはないですが、 API で連携するか、ダウンロードしたcsvファイルを生成AIに読み込ませるといった手間がかかります。
こうした手間を省略できる可能性があります。
さらに、必要な対策をまとめたレポートを自動生成し、指定した日時にメールやクラウドへ送付する、といった多段階のワークフローも構築できそうです。
病害虫情報の監視と対策手配
Agent のブラウザ機能で農業研究機関や自治体の病害虫注意報ページを定期的に巡回し、地域内でリスクが高まった際に知らせる、といった使いかたができるかもしれません。
いまどき、 SNS の情報を拾うのも有効かもしれませんね。
病害虫に限らず、高温や降雨・干ばつなどのリスクにアラートを出すこともできそうです。
圃場観察メモの音声入力と整理
スマートフォンから音声で観察メモや作業記録を投稿して、 Agent がそれをテキスト化し日付や圃場別に整理する、といったことができそうです。
複数のメモをまとめて月次報告書に編集し、Excel シートや PDF で出力する、といったことも自動化できると思います。
ユーザーは仕上がりを確認し、必要に応じて修正指示を出すだけでよくなります。
Google App Script と Google AI Studio を使えば同様のことはできますが、多少のプログラミングの知識は必要です。
それがもっと簡単にできるようになるかもしれません。
機器メンテナンスの自動スケジューリング
農機具の稼働時間や使用状況データを読み込み、適切な点検時期を計算したうえで整備工場への予約と部品発注を行うエージェントを設置します。
カレンダー連携を通じてメンテナンス予定をスタッフへ通知し、作業負荷を均等にするためのシフト調整も可能です。
経営管理への活用アイディア
顧客管理とダイレクトマーケティング
顧客管理には何かしらのアプリやサービスを用いることが多いですが、そうした取り組みを Agent が代替してくれるかもしれません。
たとえば、販売実績のデータを用いて販売履歴や顧客リストを分析し、リピーターや高単価顧客を抽出する、といった使いかたです。
Gmail 連携ができれば、メールを一斉送信し、季節のおすすめ商品や収穫体験イベントの案内を自動で送る、といった活用もできそうです。
資金繰り予測と財務レポート作成
会計ソフトから入出金データを取得し、Agent がスプレッドシート上で資金繰り表や損益分析を作成します。
仮想コンピュータ内で Python や Excel VBA を用いたシミュレーションを実行できるため、複数のシナリオを比較するレポートを短時間で作成できます。
結果を PowerPoint 資料として自動出力すれば、金融機関への説明に整えることも可能です。
補助金・助成金情報の自動取得と申請準備
Agent が国や自治体の補助金ページを定期巡回し、新規の募集要領や締切を検知すると通知します。
申請にあたってどのくらいのことができるかは未知数ですが、プロジェクトとして実施し、自社の情報をプロジェクトファイルとして登録しておけば、その情報を参照したうえで計画を作成してくれるでしょう。
Gbiz などでの申請まで半自動化できれば最高ですね。
社内タスクの統合管理と通知
Google カレンダーやタスク管理アプリと連携して、スタッフごとの作業予定や進捗を一元化します。
Agent が毎朝、当日の予定をまとめたレポートを作成し、社内SNSもしくはメールで配布するような運用ができるかもしれません。
また、作業遅延が発生した場合にはリマインダーやサポート依頼のメッセージを自動送信することで、管理者の負担を軽減します。
基本的な設計はある程度まで人が行うほうがいいかもしれませんが、現状の業務分析から、どのような情報をどのように管理するかの提案といった最初のステップから Agent が活躍してくれそうです。
市場分析と価格決定支援
Agent のブラウザ機能を用いて国内外の市場価格や需要動向を収集し、販売計画を立てることができると思います。
たとえば、ある作物の価格が高騰したり下降したりしている場合、収穫時期を変更する提案や、出荷タイミングを調整するシミュレーションをコードで実行し、その結果を資料としてまとめます。
青果市場のデータは公開されていることが多いので、それらにアクセスして市場ごとの最近の単価や出荷量のデータを収集して、どこに出荷するのが最良かを提案してもらう、といった使いかたができそうです。
おわりに
ChatGPT Agent に関心をもっていただけたでしょうか。
私自身も自身の業務への活用アイディアを考え(あるいは、活用アイディアを生成AIに考えてもらって)、実際に試してみています。
Agent モードの登場によって、自動化できる実務の幅がまた大きく広がりそうです。
仮想コンピュータ、ブラウジングツール、外部アプリ連携といった機能が統合されたことで、農業経営においても幅広いプロセスを AI に任せることが可能な下地ができてきました。
こうした自動化の準備ができれば、経営者は意思決定や戦略立案といったコア業務に専念できます。
今後も OpenAI が提供する新機能やサードパーティ連携が拡充されれば、農業分野における AI 活用はさらに進化するでしょう。