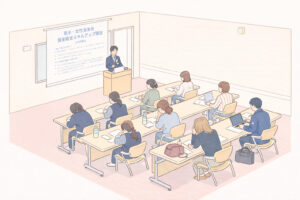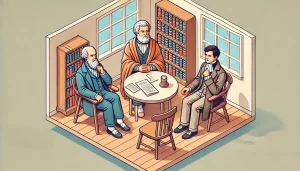議論が整理しにくい「価値」の問題
伊勢田哲治という哲学者の『倫理思考トレーニング』という本を読みました。
著者は哲学・倫理学界では知らない人がいない著名な研究者で、私も本書以外に複数の著書・論文を読んできました。
その中に一般向けに書かれた教養書として『哲学思考トレーニング』というクリティカルシンキングの参考書があり、議論をロジカルに組み立てるうえで貴重な学びを得ました。
本書『倫理思考トレーニング』は『哲学思考トレーニング』の延長線上にある続編的な位置づけの一冊で、論理だけでは結論・合意に至りがたい「価値」の問題について建設的な議論をするためのポイントが書かれています。
内容にボリュームがあり、また多数の哲学・倫理学の概念が登場するため、基礎知識がないと理解に苦労する部分があるかもしれません。
しかし、とくに組織運営や組織開発に関わる人であれば、読んでおいて損はないと思いました。
倫理の評価軸と組織の評価軸
本ブログに以前書いたことと関係する部分と絡めて、本書を一部だけですが紹介します。
倫理学の一般的な主義
倫理学には基本的な主義として徳倫理学・義務論・功利主義の3種類があり、道徳的な評価や判断において、それぞれ人格・行為・結果を重視します。
組織開発的な文脈に置き換えると、徳倫理学は能力主義(各人のスキルや人格や成長を重視)、義務論は役割主義(役職や与えられた役割を適切に遂行することを重視)、功利主義は成果主義(顧客や組織に対する実際の貢献度を重視)と親和性が高いものです。
以前本ブログでは、組織としての評価軸(人事制度等の軸)をこれら3つの主義のうちのひとつに定めることで、一貫性のある評価や決定ができるようにするべきだということを書きました(参考:主義のない人事制度は、ただ混乱を生む https://ikkei.biz/ethics-as-a-basis-of-hr/ 、主義のある人事制度をつくるために https://ikkei.biz/12-questions-to-find-values/)。
さて、私自身は功利主義の立場だという自己認識なのですが、徳倫理学や義務論にも一定の魅力を感じています。
「社会をよくすること」を目的と置く場合には論理的に功利主義に行きつくと考えるため栗主義の立場なのですが、その一方で、成長とか善い意志といったものをないがしろにするわけにはいかないとも思います。
そうした葛藤に対し、本書を読むことによって、必ずしもひとつの立場を選ばなくてもよいのではないかという視点を得られました。
(余談ですが著者の伊勢田氏も功利主義者だと思っていたのですが、その伊勢田氏が以下のような考えかたを提示されたことで私としても納得しやすくなりました。)
本書が提示する倫理的思考の4つのものさし
伊勢田氏は、倫理的な思考のものさしとして、以下の4つを提案しています。
- 結果のものさし
- ルールのものさし
- 性格のものさし
- 関係のものさし
このうち、「結果のものさし」は功利主義、「ルールのものさし」は義務論、「性格のものさし」は徳倫理学的な軸です。
「関係のものさし」はいわゆる「ケアの倫理」など、比較的新しい、人と人とのつながりを重視する考え方に由来するものです。
そしてポイントは、これらの4つのものさしのうちのどれかを使うというわけではなく、全部を使って考えようというスタンスです。
つまり、これら4つのものさしを使い、いずれのものさしで測っても許容されるような行為や判断は、1つや2つのものさしでしか評価されない行為や判断よりもよいと考える、というわけです。
なお、組織運営での評価軸(人事制度などでの評価軸)は、やはりいずれか一つの主義をベースにしたほうがよいと思います。
個々の事象については、複数のものさしを使って評価するほうがよいでしょうが、それでは時間がかかりすぎますし、権威をもっている人のさじ加減で評価がガラッと変わってしまうリスクを抱えることになります。
バリューや人事評価などは、いずれかの主義を軸として明文化しておくほうが、分かりやすくなり、納得をえられます。
4つのものさしを使ってみる
さて、4つのものさしの使いかたについて、著者が挙げている例ではないので解釈が正確ではないかもしれませんが、私なりの理解をもとに例を考えてみます。
最近自治体の首長が不祥事を起こして非難されたり辞職したりといったことが頻発していますが、こういった事象について、4つのものさしで考えてみます。
具体的な事例を取り上げるのははばかられる(個別の案件について、私としてはその人に首長であり続けるべきではないと思えるものもありますが、別に辞任するほどではないと思えるものもあります)ので、類似の事象をまとめて、やや抽象的に取り扱ってみます。
これらの首長たちは、不祥事を起こしたうえでも、首長でありつづけるべきでしょうか、それとも辞めるべきでしょうか?
結果のものさし
まず「結果のものさし」から。
結果のものさしで考えると、首長をつづけるべきか辞めるべきかは、それぞれの判断によってもたらされる結果をもとに評価することになります。
何をもって評価の対象とするのかを決めるのがまた厄介ですが、ここではとりあえず、「自治体の住民の幸福」を対象としましょう。
首長が辞任すると住民の幸福がかえって減るようであれば辞任すべきでないという判断になりますし、辞任をすると住民の幸福が増すようであれば辞任すべきという判断になります。
首長の不祥事によって住民に多少なりとも負の感情がもたらされるでしょうが、もし今の首長以上に首長として有能で結果を残せそうな人がいないのであれば、首長を辞めさせるべきではありません。
ルールのものさし
「ルールのものさし」ではどうでしょうか。
ルールというと法律を考えるかもしれません。
もちろん法律はルールの中でもとりわけ重要なものではありますが、倫理学的なルールはより根本的なもので、たとえば「人には優しくすべき」とか「嘘をついてはいけない」といった、もっと基本的なところから考えます。
それに、法律が必ずしもよいルールだとも限りません。
そこで、はたしてどのようなルールをもとに評価するかを考える必要があります。
ただし、今回はそこから考えるととても手に負えないので、いったん法律や条例といった社会的にある程度の合意のあるルールをもとにしましょう。
この場合、もしその不祥事が法律や条例に違反する種類のものであれば、首長には首長の資格なしとなります。
反対に、たとえ世間的には非難の対象になるような行為だったとしても、別に法律や条令に反してはいないのであれば、その不祥事をもって首長を辞任に追い込むことは正当化できないのではないでしょうか。
性格のものさし
次に「性格のものさし」。
これはその人がよい意図や人格をもっているのかどうかということを評価の対象とするものです。
よい結果や行為であったとしても、その背後にある意図がよこしまなものだったら手放しでは評価し難いものです(たとえば、盗みに入ろうとして家を物色していたら、たまたま他の泥棒に出くわして捕まえるような場合)。
反対に、悪い結果や行為でも、その背後に何かしらよい意図があったのであれば、情状酌量の余地があるかもしれません(典型的に挙げられる例は、貧しい家庭の親が子どもを病気から救うために薬を盗むような場合)。
これもまた、どのような意図や人格がよいものなのかを考えることが必要になりますが、いまはあまり深入りしないことにしましょう。
性格のものさしで考えると、不祥事を起こした首長がどのような意図や人格をもっていたのかを検討することになります。
たとえば、その不祥事を悪いことだとは思わずに(知らずに)おこなったとか、むしろよいことだと信じておこなったといったことであれば、このものさしでは非難されるべきではありません。
しかし、悪いことだと知ったうえでおこなったり、露見したあとも保身のために意図的に嘘を重ねたりするのであれば、それは非難されるべきでしょう。
関係のものさし
最後に「関係のものさし」。
評価の対象となっている人が取り結んでいる関係によって、評価の内容が影響を受けるというものです。
ケアの倫理では、両親は子どもに対し、たとえ法律などで定められていないようなことでも、子どもが必要とするケアであれば提供すべきでしょう。
このような、人と人との関係を考慮する倫理的な評価のものさしです。
本書では「専門職倫理」についても語られていますが、首長はある種の専門職として、その自治体の住民に奉仕すべき関係をもっているでしょう。
もしその関係をないがしろにするような不祥事であれば、関係のものさしからも、辞任すべきという判断になりそうです。
しかしその不祥事がとくに住民に対する責任とは無関係のものであったり、首長が首長としての住民に対する責任は果たしているようであれば、首長という立場から追いやることはできないでしょう。
不祥事を起こした首長は辞任すべき?
このように、倫理的な評価をしたい事象に対してこれら4つのものさしを順番に当てはめて評価を行い、判断をします。
たとえば、よこしまな思いから不祥事を起こした(性格のものさし)としても、それによって引き起こした損失より首長をつづけることによる住民の幸福の増加分のほうが大きく(結果のものさし)、とくに法律や条令によって首長としての資格を失うような不祥事でもなく(ルールのものさし)、住民に対する責任も果たしている(関係のものさし)のであれば、首長を継続してもよいのではないか(あるいは、首長を継続するべきではないか)といった判断になりそうです。
しかし、たとえばより首長として住民をもっと幸福にできそうな人がいて(結果のものさし)、公職選挙法など何かしらの法律を犯しているかグレーゾーンで(ルールのものさし)、単に利己的な目的のために起こした不祥事であり(性格のものさし)、住民のことをないがしろにしている(関係のものさし)のであれば、間違いなく辞任するべきという判断になるでしょう。
もちろん、これら4つのものさしの間の重みづけをどうするのかや、それぞれのものさしでの評価が本当にこれでよいのかなど、議論の余地はいくらでもあります。
しかし、何も判断基準がないところで各人が好き勝手なことを言うよりは、4つのものさしを軸として意見を出すほうが、建設的な議論になるでしょう。
このようなやりかたは、仕事においてもプライベートにおいても、人と関わる限り役に立つものだと思います。
組織として、コミュニティとして、よりよい議論や話し合いを行うために、本書に挑戦してみてはいかがでしょうか。